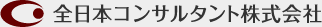京都線東寺・竹田間連続立体交差事業
(高架橋デザイン・URT桁高架橋)
| 発注者 | 近畿日本鉄道(株) |
|---|---|
| 路線名 | 近鉄京都線 |
Ⅰ鉄道高架橋デザイン設計
本区間の連続立体交差事業は、6ヶ所の踏切を廃止して交通渋滞の緩和を図り、あわせて周辺地域の一体的なまちづくりに向けた都市基盤整備として計画されました。古都京都にふさわしい高架橋をつくるために学識経験者らによる「近鉄京都線高架デザイン検討委員会」が設置され、当社もそのワーキンググループの一員として参画しました。同委員会で検討した結果、周囲の環境に圧迫感を与えないような配慮として、高架橋については南部の躍進を象徴した「ダイナミックさ」を基調としながら、その中に京都らしい流麗さを表現して、小さなアーチが連続する小気味よいデザインとしました。
本高架橋の主なデザインディテールは、以下のとおりです。
- ・縦梁は、下面が半径9.85mの円弧、外面にはアーチ形状の化粧形枠を使用する
- ・アーチの連続性で調整単版にもアーチ状の垂壁を設ける
- ・柱は円形とし、柱頭部強調のため縦梁側面より外側に出す横梁も円弧とする
- ・壁高欄は場所打ちとし、天端には「笠木」を設ける
- ・軌道床版下側に化粧形枠を採用し、デザインの統一性を強調
- ・調整単版の遊間目地が外側から見えないように、落とし込み形式とする
-
・架線柱は鋼製の門型テーパーポールを採用し、特殊高圧線はダクト内に納めて線路より上面の
輻輳する架空線のデザイン的な単純化を図る
-

[平面図]
-

[側面図]
-

[近鉄東寺駅付近]
-

[鉄道高架橋]
Ⅱ鉄道既設盛土区間を高架橋に再構築(URT桁高架橋)
連続立体交差化事業において、仮線から高架橋に切り替えた後も残存する東寺駅より南側の延長約76mの石積み盛土をRCラーメン高架橋に改築する設計業務を実施しました。
用地と構造上の条件より線路移設に制限があるために、施工法の比較検討を行った結果、当該区間においてURT工法により線路を仮受けした後、その直下でURTエレメントを本設スラブとして利用した高架橋を構築します。
工事の特長
◆大規模な仮受け:長期間 約1年
長区間 約76m
◆全国で初めてRCラーメンの高架橋のスラブとして利用
長区間 約76m
◆全国で初めてRCラーメンの高架橋のスラブとして利用
URTエレメントをスラブとして利用するに当たっての対策
◆地震時水平力の伝達 ⇒ アンカーボルトにより、エレメントと上層梁と接続
◆床版の面内剛性の確保 ⇒ 継手部に高流動コンクリートを充填、エレメント間に鋼板溶接
◆床版の面内剛性の確保 ⇒ 継手部に高流動コンクリートを充填、エレメント間に鋼板溶接
将来の発展性
市街地に多数残存する営業線路の石積盛土は、目地が老朽化し構造上問題が生じていたり、高架下の有効利用の必要性などから、高架橋への改築の需要は全国的に増えてきています。今回の工事により開発された設計、施工技術はそのような新たな需要により引き継がれ、ますます発展することが期待されます。
◆市街地における鉄道構造物の改良
◆高架下の有効利用
- ○交通阻害が少ない。
- ○振動騒音が少ない。
- ○夜間作業が少ない。
- ○軌道への影響が少ない。
◆高架下の有効利用
-

[設計図]
-

[高架橋の構築]
-

[十条駅①]
-

[十条駅②]
-

[上鳥羽口駅]
-

[十条駅③]